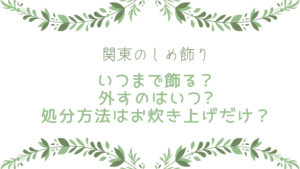
関東のしめ飾りはいつまで飾るのか、外すのはいつなのか、処分方法はお炊き上げだけなのかについてまとめてみました☆
この時期になるといつも「しめ飾りっていつ外すのが正しいのかな?」と気になります。
せっかく年神様をお迎えした行事の締めくくりをきちんと行って、気持ちの良い一年を送りたいですよね(*’ω’*)
この記事では
- 関東のしめ飾りはいつまで飾るのか
- 関東のしめ飾りを外すのはいつなのか
- 関東のしめ飾りの処分方法はお炊き上げだけなのか
についてわかりやすくお知らせします。詳しくは本文でお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
関東のしめ飾りはいつまで飾る?
しめ飾りはいつまで飾るかについては以下の通りです。
「松の内」とはお正月の事始めから神様がお帰りになるまでの期間のことを言います。
関東でいう「松の内」とは1月7日までになります。この期間まではしめ飾りは飾っていてOKですよ。
ただ1月7日になったらいつ外せば良いのか気になりますね。
関東のしめ飾りを外すのはいつ?
関東のしめ飾りを外すのはいつかについては以下の通りです。
1月7日に「七草粥」を食べる習慣は江戸時代から広まったそうですが、『今年も家族みんなが元気で暮らせますように』という願いながら頂きます。
朝に「七草粥」を食べた後にしめ飾りを外すので、午前中に外すのが縁起良いのではないでしょうか(*’ω’*)
ただここも地域の風習にもよるところがあるそうなので、気になる方は氏神様など近所の神社へ確認されるといいですよ。
関東のしめ飾りの処分方法はお炊き上げだけ?
関東のしめ飾りの処分方法については以下の通りです。

お炊き上げとどんど焼きって違うの?
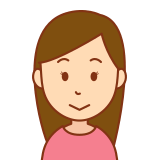
どんど焼きとは火祭りの行事で、お炊き上げの一種です。
お炊き上げ
どんど焼き
全国各地で見られる風習で、年神様をお見送りする火祭りの行事のことを指し、縁起物を燃やすことで無病息災・家内安全・商売繁盛などを願います。
どんど焼きは1月15日に行われますので、それまでにお近くの焼いてくれる神社に持って行くといいですよ(*’ω’*)
ちなみに小正月に行う火祭りの行事で地域により呼び名が異なっており、「左義長」「さいと焼き」「どんどん焼き」「おんべ焼き」「鬼火焚き」とも呼ばれています。
もし焼いてくれるところがない場合、そのまま捨てるのは気が引けますよね。その際は以下のようにするといいですよ。
- 飾りをお塩で清める
- 新聞紙などに包んで燃えるゴミへ
こうすることで一通りの行事としても区切りにもなりますし、感謝・お願いの気持ちを込めてお塩で清めますのでそのまま捨ててしまうより全然気持ちが違います。
プラスチックなどの分別もお忘れなく注意してくださいね。
関東のしめ飾りはいつまで飾るまとめ
- 松の内と呼ばれる期間は飾ったままでOK※関東は1月7日
- 朝に七草粥を食べてからしめ飾りを外す
- どんど焼きで焼いてもらうのが好ましいが、難しいなら飾りを塩で清めて燃えるゴミへ
以上のことがわかりました。
[知っているようで知らないしめ飾りの決まり]というのはなかなか難しいところがありますよね(;^ω^)ただ年神様をお迎えするものですので、きちんとやりたいという思いもあるかと思います。
その年が良い年になるように心を込めて行えば例え間違っていたとしても悪いように転がるということはないと思いますが、手順通りに行えばさらに気持ちよくその年を迎えることができると思いませんか(*’ω’*)
皆さんもしめ飾りを正しく外して、その年一年の無病息災・家内安全・商売繁盛などを願いましょう。

